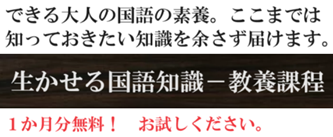A) ×
※正しくは「中秋の名月」です。人偏の付いた「仲秋」は陰暦8月のことをいいます。陰暦8月15日と日まで特定した名月なら、「中秋」と書かなければいけません。
※「仲」という漢字には「中間」の意味があります。陰暦では7月から9月までが「秋」ですから、中間の8月が「仲秋」になります。また7月は「孟秋」。「孟」には「はじめ」の意味があるからです。「孟」の逆の「すえ」を表すのが「季」です。ですから、9月は「季秋」と呼ばれます。
「孟・仲・季」は当然ながら他の季節にも使われます。春なら、1月が「孟春」、2月が「仲春」、3月が「季春」というように・・・。
現在では「孟」の代わりに「初」、「季」の代わりに「晩」を使い、「初冬・仲冬・晩冬」などと呼ぶのが一般的ですが、「孟・仲・季」を使うことも覚えておきましょう。
※「仲」という漢字には「中間」の意味があります。陰暦では7月から9月までが「秋」ですから、中間の8月が「仲秋」になります。また7月は「孟秋」。「孟」には「はじめ」の意味があるからです。「孟」の逆の「すえ」を表すのが「季」です。ですから、9月は「季秋」と呼ばれます。
「孟・仲・季」は当然ながら他の季節にも使われます。春なら、1月が「孟春」、2月が「仲春」、3月が「季春」というように・・・。
現在では「孟」の代わりに「初」、「季」の代わりに「晩」を使い、「初冬・仲冬・晩冬」などと呼ぶのが一般的ですが、「孟・仲・季」を使うことも覚えておきましょう。
B) 〇
※里芋を供えたことから、こう呼ばれます。
※里芋を供えたことから、こう呼ばれます。
C) 〇
※陰暦9月13日の月を、「栗名月」・「豆名月」といいます。また、「十三夜(じゅうさんや)」・「後(のち)の月」ともいいます。
※陰暦9月13日の月を、「栗名月」・「豆名月」といいます。また、「十三夜(じゅうさんや)」・「後(のち)の月」ともいいます。
D) 〇
※陰暦8月16日:「十六夜(いざよい)の月」、17日:「立待ち月」、18日:「居待ち月」、19日:「寝待ち月」、20日:「更(ふけ)待ち月」です。
※陰暦8月16日:「十六夜(いざよい)の月」、17日:「立待ち月」、18日:「居待ち月」、19日:「寝待ち月」、20日:「更(ふけ)待ち月」です。
(注1) 「十六夜(いざよい)の月」:「いざよう」はためらう、躊躇(ちゅうちょ)するの意味。月が出るのをためらっているように見えることから。
/「立待ち月」・「居待ち月」などは、日を追うごとに遅くなる月の出を待つ人の様子からできた呼称です。
/「立待ち月」・「居待ち月」などは、日を追うごとに遅くなる月の出を待つ人の様子からできた呼称です。
(注2) 陰暦8月15日は今の暦でいつなのか?は年によって変わります。
今年の「中秋の名月」は9月29日とのことです。ただし、満月もこの日。※詳しく知りたいなら、国立天文台のサイトがお勧めです。→国立天文台サイト
今年の「中秋の名月」は9月29日とのことです。ただし、満月もこの日。※詳しく知りたいなら、国立天文台のサイトがお勧めです。→国立天文台サイト